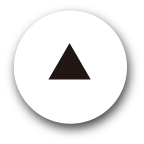今回訪問したのは、石川県加賀市にある伝統工芸・九谷焼の窯元「九谷陶苑」。当主は、加賀伝統の赤絵細描(あかえさいびょう)の技法を受け継ぎ、現代的九谷赤絵を創造し続ける山本芳岳さん。次男でろくろ師の山本浩二さん、三男で絵付師の山本秀平さんといっしょに九谷焼の伝統と新たな魅力を世の中に発信し続けています。

親から子へ受け継がれた
伝統の加賀九谷。
九谷焼は石川県南部で作られる色絵陶磁器の総称で、はじまりは江戸時代。陶石が発見されたことがきっかけで陶石の産地となった九谷村にちなんで「九谷焼」と呼ばれるようになりました。また、山水、花鳥など絵画的で大胆な上絵付けによる装飾が美しく、その彩法は時代の流れとともに進化。青九谷、赤九谷など、さまざまな画風が生み出され、今もなおその可能性は広がり続けています。九谷陶苑の当主・山本芳岳さんは、大学卒業後に井上芳景氏に弟子入りし、「九谷赤絵細描」の運筆、上絵釉薬の薫陶を受けます。2年間の修行期間を経て、九谷焼の販売をしていたご実家に戻り作陶活動をはじめたのが、およそ40年前。その後、長く活動を続けるなかで、自身が継承した赤絵細描の技術の継ぎ手を探していたそうです。『息子しかいなかったんです。ずっと加賀の伝統を受け継いでいるのはうちだけで、他にも赤絵はありますが、技法から何から全く違う。私の代が終わったら、加賀九谷が途絶えてしまう。だから、息子しかいなかった』。芳岳さんの願った通り、加賀の地で脈々と受け継がれてきた伝統は、ろくろ師・浩二さんと、絵付師・秀平さんへと伝承されていきます。

兄弟が身につけた
それぞれの伝統技法。
子どもの頃からものづくりが好きだった浩二さんと、絵を描くのが好きだった秀平さん。芳岳さんの背中を見て育ったお二人は、同じ九谷焼の道を志します。浩二さんは、仕入れてきた素地に絵付けをする芳岳さんの背中を見て、自ら素地をつくれる「ろくろ師」へ。秀平さんは、芳岳さんの描く赤絵に憧れて「絵付師」へ。それぞれ歩みを進めます。兄弟はその後、それぞれ九谷焼ならではの伝統技法を身につけることに。浩二さんが身につけたのは『型打ち技法』。ろくろで成形した素地を型に押し当てて成形する方法で、均整のとれた美しいフォルムの器を量産するのに適しています。ただし、型打ちをするには、熟練の技術が必要。浩二さんは2年間の弟子入りの末、この伝統技法を習得しています。秀平さんは再現不可能と言われていた伝統技法「砡質手(ぎょくしつて)」の再現に成功。砡質手とは赤絵の名工だった中村秋塘氏が生み出した技法ですが、その技法に関する継承を誰も受けていなかったため、現代では幻の技法と言われていました。そんな「砡質手」の再現に、1年の歳月をかけて成功した秀平さんは、『白砡描割(はくぎょくかきわり)』という新たな技法を完成させて、世の中を驚かせたのです。

※2025年8月時点の情報です
九谷焼という伝統文化を
後世へと伝えていくために。
九谷陶苑が受け継いできた伝統の赤絵細描の技術は、途絶えることなく秀平さんへと継承。九谷焼という文化そのものをさらに伝え広げていくために、芳岳さんは展示会やイベントなどに積極的に参加されているそうです。一方の浩二さんは、伝統の加賀赤絵をもっと多くの人に知ってもらうために、「カタチ」にこだわりたいそう。『やっぱり、最初にお客さんの目に入るのは、カタチ。カタチが気になって手に取ってもらい、赤絵細描の美しさを知ってもらうということになると思うので、ろくろ師として、目をひくカタチにこだわっていきたいですね』。また秀平さんは「白砡描割」の技法をもっと突き詰めて、アレンジしていきたいと考えているようです。『今、白砡描割は「赤」でつくっていますが、九谷焼は五彩色がメイン。青や黄などでもつくってみたいですね』。つくった作品は奥様が撮影をして、SNSでも積極的に発信されているそうです。加賀九谷を受け継ぐ、兄弟の伝統工芸士。受け継いだ技法に、新しい感性を取り入れて、新時代の九谷焼が、ここ加賀の地で動きはじめています。

石川県加賀市のお礼品
【高島屋選定品】
赤絵細描金襴小紋ぐい呑










































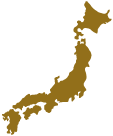
 ランキング
ランキング