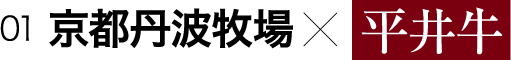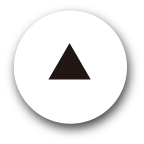豊穣の地において、素材のクオリティを追い求める生産者。その手によって育まれたお礼品を、美味なる一品に仕上げる地域の料理人。それぞれのプロフェッショナルたちの、モノづくりへの熱い想いを通して、「ふるさと納税」の魅力をお伝えします。

ふるさとから思いを込めて家庭の食卓へ
のどかな田園風景が広がる南丹市に、料理人垂涎の黒毛和牛を育てる牧場があります。有名精肉店や格式のあるレストランなど限られた取引先に卸され、家庭ではなかなか口にできなかった平井牛。丹精込めて育てた牛を、全国の皆様にお届けしたい。そんな生産者の思いが、ふるさと納税で実現しました。

- 代表取締役社長平井 和恵 さん
- 大学卒業後、一般企業勤務を経て、10年前から家業である畜産の仕事に従事。現在では子牛の買い付けから、牧場での牛の世話、出荷に関する各種取引まで牧場経営全般を担当。
手塩にかけた平井牛は
黒毛和牛のなかでも格別の存在
「黒毛和牛は日本が誇るべき財産。業界の高齢化が進むなか、黒毛和牛の価値を高め、未来に残したいという思いで、日々の仕事に取り組んでいます」家業である京都丹波牧場の経営を担う平井和恵さんは、幼いころから父のもとで、牛に親しんできたといいます。「牧場の仕事をするようになって、先代から最初に教えられたのが子牛の見極めです。三代祖、四代祖にさかのぼって血統をチェックし、さらに市場で実際に子牛を見て、どんな体つきになるかをイメージするんです」平井牛は、口に含むとすべるように溶け出すきめ細かな脂が最大の特徴。その力を秘めた子牛を選別し、「牛が完熟する」までじっくり育てるそうです。「果物は完熟がおいしいように、牛も長期肥育することで肉の旨味や脂の質が向上します」長く育てるとコストやリスクも高まりますが、牛の様子を日々つぶさに観察し、最高の状態で出荷することに心を砕きます。「肉牛は経済動物といわれますが、一つの命であることには変わりありません。『我が子と一緒だと思って、最後まで手をかけてあげろ』という先代の教えをいつも心に留めています」大切に育てた牛を見送るときは、やはり感慨深いといいます。「ふだんは卸業者に一頭売りという形で出荷しますので、なかなかご家庭とつながる機会がありません。ふるさと納税を通じて、平井牛のおいしさを全国の皆様にお届けできるのは、本当に嬉しいことですね」


平井和恵さんはじめ従業員の方々で丹念に牛の世話をする毎日。常に牛舎は清潔に保たれ、風通が工夫されているため、牛にとってはストレスフリーな環境が整っている

一般的に約28 カ月で出荷される肉牛を30〜36カ月になるまで手元で育てる

- 京都丹波牧場
- 農畜産に適した気候風土を持つ南丹地方で明治元年に創業。自然の恵みと日々の努力で平井牛の理想とする肉質を追求し、数々の賞を受賞。
〈京都丹波牧場〉京都平井牛
ロースすき焼き用
750g


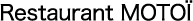 シェフ前田 元 さん
シェフ前田 元 さん- 京都で古書店を営む家に生まれる。10 年間、中国料理の修業をしたのち、フランス料理を学ぶために渡仏。帰国後もフレンチの修業を積み、2012 年にレストランモトイを開業。
軽やかな脂の質に驚きました
フレンチとも相性抜群です
「京都丹波は食材の宝庫。肉も野菜も、良いものが揃います」自ら駆け回って集めた食材を振る舞う「馳走」を体現する前田シェフは、京都丹波の食材に絶対の信頼を置いています。「とりわけ平井牛には、昔から興味があったんです。脂の質が軽やかで、自分の店で使ってみたいと思っていたら、平井さんに偶然ご来店いただいて……」そんな縁もあり、関西の食通が集まるレストランモトイでは、オープン2年目から平井牛を提供。今回は皆様にも平井牛のおいしさを堪能してほしいと、ご家庭でもつくれるレシピを考案いただきました。「平井牛の脂のキレとマスタードの酸味がよく合い、またサラダ仕立てにしたことで、さっぱり食べられます。和牛とフレンチの共演をお楽しみください」

- 見た目もおいしい平井牛のサラダグルマン
トマトのタブレと
クレソンのメランジェ -
材料(2 人分)
- 平井牛
(すき焼き用スライス)…4 枚 - クレソン…8 束
- 玉ねぎ…1/2 個
- トマト…1 1/2 個
- クスクス…30g
- ディジョンマスタード…大さじ1
- シェリービネガー…小さじ2
- オリーブオイル…大さじ2
- 塩、黒こしょう…適量
- 平井牛
- 作り方
- ① クスクスに熱湯をひたひたに注ぐ。ラップをして約5分蒸らしたら、ほぐすようにして、オリーブオイル(分量外)を混ぜ込み、粗熱を取る。
② トマトを湯剥きする。1個は一口大に、1/2 個は3 ㎝の角切りにする。
③ ①に②の角切りにしたトマトを加え、塩(分量外)で味を調える。
④ クレソンを水洗いして適当にちぎり、水気を切る。
⑤ 玉ねぎはスライスし、水にさらして辛みを抜き、水気を切る。
⑥ A を混ぜ、塩、黒こしょうで味を調える。
⑦ 平井牛を三等分に切り、熱したフライパンに1枚ずつ広げ、サッと焼く。
⑧ ⑦の焼き上がりに軽く塩(分量外)を振り、別皿によけておく。
⑨ ボウルに②の残りのトマト、④、⑤を入れ、⑥で和える。
⑩ 皿に③、⑧、⑨の順に盛りつける。


- オープン以来、メディアにたびたび取り上げられてきた京都・御所南の名店。築100年の日本邸宅を改装し、古都のムードに洒脱さが融合した空間に。シェフの料理にも通ずる大胆で革新的な意匠にも注目。

懐かしい味は郷土の誇り老若男女に愛される一品
岐阜県民が誇るご当地ブランドといえば、郡上市の「明宝ハム」は外せません。なかでも創業以来の味を守り続けるプレスハムは、食卓を彩る一品として、笑顔を呼ぶギフトとして、世代を超えて愛されています。

- 工場長石田 哲仁 さん
- 生の豚肉の仕入れから、工場での実作業まで、幅広い業務に従事。子どものころから味わっていた明宝ハムの味を守り、製造技術のさらなる向上を目指そうと日々奮闘。
手づくりの味を
守り続けることでふるさとに貢献
長良川の流域にのびる飛騨せせらぎ街道。風光明媚な街道の中間点に、明宝ハムの工場があります。工場といっても、その製造はほとんどが手作業。生の豚もも肉から丁寧に筋を取り除き、一つひとつ切り分けるところから作業がはじまります。「片脚8㎏ほどの肉の塊を、すべて人の手でさばいています。臭みの出やすい冷凍肉は使わず、肉の鮮度にはこだわっています」と工場長の石田哲仁さん。豚肉本来のおいしさやプリッとした独特の食感を引き出すために、昔から一貫した製法は変わりません。昭和28年に、山間部の食生活改善と畜産振興を目的にスタートしたハムづくり。過疎化が進んだ現在は、雇用の場としても重要な役割を担います。安易な機械化をせず、愚直に手づくりを貫くことが、ハムのおいしさだけではなく、ふるさとを守ることにもつながっているのです。

働いているのは地元の女性が多く、中には20年以上在籍のベテランも

手作業で丁寧に筋を取り除く

リテーナーの中で膨張することで独自のひし形が浮かび上がる

- 明宝特産物加工
- 昭和28年に農協の事業としてスタートしたハムづくりがルーツ。昭和55年、NHKの『明るい農村』で明宝ハムが取り上げられ多くのファンを獲得。一時は「幻のハム」と呼ばれるほどの人気に。その後、地域おこしの特産品として事業を成長させ、平成30年には新工場も完成。ハムづくりを間近で見られる工場見学が好評。
〈明宝ハム〉明宝ハム・
ソーセージの
3本詰合せ


- ぎふ水琴亭 料理人山田 学 さん
- 和食店、料亭などで経験を積み、2019年よりぎふ水琴亭の料理人に。明宝ハムのホームページ「名店料理長監修レシピ」のコーナーにて、アイデア満載のメニューを発表。
大人になっても色褪せない思い出の味
岐阜出身の山田さんは、子どものころから明宝ハムが身近にあったといいます。「土曜日のお昼ごはんに、母が明宝ハムをさっと焼いてくれると嬉しかったね。父が酒の肴にしていたのも覚えています。それを横から、つまみ食いしたりして」和食の料理人として腕をふるう現在も、ご自宅では明宝ハムをよく食べるといいます。「明宝ハムといえば、しっかりと弾力のある歯ごたえ。今回紹介するレシピでは、蓮根饅頭の食感との組み合わせが面白いと思います。県外の方にも、ぜひ明宝ハムをいろんな形で楽しんでほしいですね」

- 食感の妙に頬がほころぶ明宝ハムと蓮根饅頭
-
材料(1人分)
- 蓮根(すりおろし)… 80g
- 大和芋(すりおろし)…4g
- 明宝ハム…40g
- 片栗粉…10g
- 長ねぎ…8㎝
- 揚げ油…適量
- つゆ…60cc
※市販のめんつゆを使って、「つけつゆ」の規定の分量でつくってください。
- 作り方
- ① 蓮根のすりおろしはキッチンペーパーなどで包んで絞り、水分を除いて約66gにする。
② ボウルに①、5㎜角に切った明宝ハム、大和芋のすりおろしを入れ、混ぜ合わせる。
③ ②を2つに分けてそれぞれ丸くまとめ、片栗粉をまぶし、170℃に熱した揚げ油で3分30秒揚げる。
④ 長ねぎを半分の長さに切り、グリルで焼き目をつける。
⑤ 小鉢に③を盛り、温めためんつゆをかけ、④を添える。

- ぎふ水琴亭
- 150年以上の歴史を持つ老舗。幕末から受け継がれた趣深い空間のなかで、名物のうなぎ料理や懐石料理を提供。同店を愛した原三渓直筆の襖絵やゆかりの品にふれることも。

心尽くしの一服に歴史と文化が香る
加賀や金沢でほうじ茶といえば、棒茶のことを指します。お茶の葉ではなく、主に茎を焙じ上げた棒茶は、普段づかいの番茶として親しまれていますが、丸八製茶場の「献上加賀棒茶」は至福の一服。献上の名にふさわしい、芳ばしい香りと澄んだ飲み口を楽しめます。

- 製造課リーダー長崎 貴也 さん
- 焙煎職人として活躍しながら、現場のリーダーも担う長崎さん。7人家族のにぎやかな家庭に育ち、「加賀棒茶で日本の家庭から失われつつある団らんを取り戻したい」との思いを抱く。
「加賀棒茶」の奥深い魅力を
日本中のお客様に味わってほしい
石川県のお隣り、富山の直営店「syn」では、加賀棒茶の多彩な飲み方を提案。副店長の有沢さんは、「ラテやスパークリングティーにしてもおいしいんです」と日々いろいろな味わいを探求しています。「子どものころから地元のほうじ茶に親しんでいましたが、献上加賀棒茶にはまた違った魅力があります。澄んだ色や香りに、心が落ち着く感じがするんです。お客様からも、『なぜこんなに香りがいいの』と驚きの声があがります。ふるさと納税を通じ、全国のお客様にもぜひ楽しんでいただきたいですね」

上段から130℃、下段から190℃の遠赤外線を1℃単位で微調整

10分に一度、焙煎状態を試飲してチェック

本社工場敷地内の「双嶽軒(そうがくけん)」ではほうじ茶をいただきながら、茶の奥深さを体験出来ます(要予約)

(左)焙煎前の原料(右)焙煎後の棒茶

- 丸八製茶場
- 創業は文久3年(1863年)。加賀藩前田家の製茶奨励政策によって開かれた茶どころ・打越で暖簾をあげ、昭和26年に現在の本社を構える動橋に移り、地域とともに発展。明治時代からお茶の茎を使った加賀棒茶を手がけ、「献上加賀棒茶 」の開発で新たな価値を生み出した。
〈丸八製茶場〉加賀棒茶
お茶セット B


- syn 副店長 日本茶インストラクター有沢 美由記 さん
- 日ごろの接客では「お茶の魅力について、お客様と楽しく語らっています」という根っからのお茶好き。店舗のスタッフとともに各種企画やメニューの考案なども手掛ける。
「加賀棒茶」の奥深い魅力を
日本中のお客様に味わってほしい
石川県のお隣り、富山の直営店「syn」では、加賀棒茶の多彩な飲み方を提案。副店長の有沢さんは、「ラテやスパークリングティーにしてもおいしいんです」と日々いろいろな味わいを探求しています。「子どものころから地元のほうじ茶に親しんでいましたが、献上加賀棒茶にはまた違った魅力があります。澄んだ色や香りに、心が落ち着く感じがするんです。お客様からも、『なぜこんなに香りがいいの』と驚きの声があがります。ふるさと納税を通じ、全国のお客様にもぜひ楽しんでいただきたいですね」

- 寒い季節にほっこりおいしい加賀棒茶ラテ
-
材料(1人分)
- 献上加賀棒茶…9g(献上加賀棒茶ティーバッグの場合は3個)
- 熱湯…180ml
- 牛乳…50ml
- 砂糖…5g(角砂糖1個分)
- 作り方
- ①急須に棒茶を入れ、熱湯を注ぎ、2分30秒おく。
②マグカップに砂糖を入れ、①を注ぐ。よく混ぜて砂糖を溶かす。
③②にミルクウォーマーで温めた牛乳を入れ、泡をふんわりと乗せる。
※砂糖と牛乳の量はお好みで調整してください。

- お茶の香りが鮮烈に引き立つ加賀棒茶
スパークリング -
材料(1人分)
- 献上加賀棒茶…6g(献上加賀棒茶ティーバッグの場合は2個)
- 熱湯…50ml
- 氷…約100g(四角い氷5〜6個分)
- 炭酸水…150ml
- 作り方
- ① 急須に棒茶を入れ、熱湯を注ぎ、1分半〜2分おく。
②①に氷を入れ、炭酸水を注ぎ、1分ほどおく。
※急須に炭酸水を注ぐことでお茶の風味とほどよく融合し、角がとれたまろやかな味わいになります。
③②を茶こしで濾しながら、よく冷やしたグラスに注ぐ。

- syn(丸八製茶場 富山駅直営店)
- 「きときと市場とやマルシェ」内にあり、献上加賀棒茶をはじめとするお茶のほか、地元の日本酒も提供。2020年初夏にリニューアルし、お茶や日本酒を気軽に楽しめるスタンディングスペースを設置。










































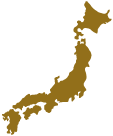
 ランキング
ランキング